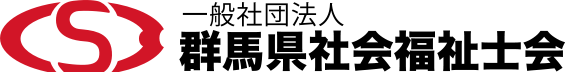レッツ・ホール・ハンズ第5回勉強会 開催報告
群馬県地域生活定着支援センター所長である高津勉氏をお迎えし、「社会構造の変化から今を考える」をテーマにお話しをしていただきました。 本来は昨年8月に予定していた第1回目のゲストスピーカーでしたが、台風の影響により延期となり、念願の開催となりました。 第1部の講義の中で、私たちソーシャルワーカーが支援をしていくうえで大切なこと、改めて考えさせられるキーワードがたくさん盛り込まれていました。(以下、お話しいただいたことを抜粋) ・犯罪は表に出ている行為。問題行動は見える。しかし福祉が支援をするのは見えない部分。犯罪は支援者の対応や理解の仕方によって大きく変わってしまう。罪を犯した人の裏に何があるのかをきちんと考える! ・今までやってこなかったことに対して「出来ない。」と言ってしまう事が見受けられる。今、目の前で困っている方に何ができるかを考えることが大切! ・他機関・多職種連携のメリットについて。色々な考え方を知れるだけでなく、支援者としての姿勢を確認させてくれるものさし。「ぐんま・つなごうねっと」と出会い、仕事ではないのに一緒に動いてくれることに感謝。お互いにリスペクトができるのは大事なところ。 ・自分たち(支援側)がいるから支援されている方が落ち着いて生活できているという「過信」をしてしまうこともある。→その方たちは本当に本音を言えているのか。 ・社会構造の変化とともに「孤立」が増えている。昔は軽微な問題が起きても「地域の中のおせっかい」で物事が解決できていた。今は隣に誰が済んでいるか分からない時代。地域の中で支えられなくなった結果、軽犯罪法違法などが表面化し、力の弱い方が排除され刑務所へ…。 ・罪を犯してしまう人の中にはIQが低い人が多い。支援が必要な人に必要な支援が届かなかった結果として犯罪を起こしてしまうことがある。 ・高齢者などは見えない孤立で罪を犯してしまう。地域活動に参加したりと一見そのように見えなくても、役割が無い、寂しいなどの心理的閉塞感などが理由だったりする。 ・制度が整わないのに少年法だけが改正されてしまった。「虞犯」から18、19才が排除され、関われる機関もない。戻れる場所が無ければ、犯罪を繰り返してしまう恐れも…。子どもの問題に着手する時にはこの部分をきちんと考える必要がある。 ・インクルージョンから「ビロンギング」へ。その場所に自分たちが「居たい。」という気持ちで主体的に役割を持ってそこにいることが大切。 ・社会は「申請主義」。社会的に弱い人は生きづらさを抱えており、必要な支援を受けられない。その様な人たちをどう「面」で支えていくかが重要。 行政にとって困った人→本人が何に困っているか想像するべきところである。 ・連携と押し付けの違い→役割分担をし過ぎると縦割りになる。その狭間をどう埋めるか。顔の見える関係性が重要!
実行可能か不可能かは支援者の置かれている環境に左右されるかもしれませんが、「誰のための支援なのか、ちゃんとその人を見ているのか。」そのことを念頭に置き、行動していきたいと強く思いました。
第2部の懇親会は、同じ場所でおいしい中華を楽しみながら行われました。
自己紹介では皆さんの意気込みや熱い想いを聞くことができました。その想いに触発された方もいたのではないでしょうか。ここから今後の多職種連携も生まれてきそうな気配もありました。
講師の高津氏へのリスペクトも含め、とてもいい雰囲気で幕を閉じました。
次回は行政書士会の皆さまを講師にお迎えし、テーマ「ペットのためにできること~ペット法務と多頭飼育崩壊の現状」
4月12日(土)に開催です。
(文責:山田 晶子)