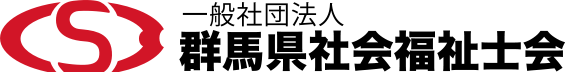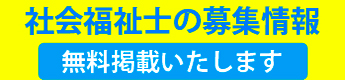社会福祉士は障害や加齢、環境上の理由によって日常の暮らしに支障がある人に寄り添い、暮らしをサポートします。
ソーシャルワーカーとも呼ばれ、各種相談・支援などを行います。群馬県社会福祉士会は群馬県内で活動する社会福祉士の価値・倫理・知識・技術の向上を目指して研修・交流を行っています。
群馬県社会福祉士会は
群馬県内で活動する社会福祉士の
スキル向上を目指す社会福祉士の団体です
「仲間1000人計画」実行中!
群馬県社会福祉士会には約700人の会員がいます。今「仲間1000人計画」実行中です!
会員になると、会員限定の基幹研修や、成年後見人になるための研修、分野別の研究や地域別での交流など、社会福祉士として活動するための活きたスキルを得ることができます。
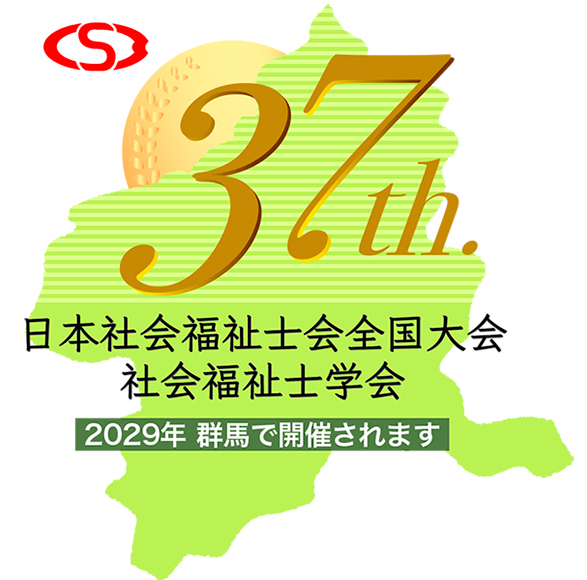
お知らせ
- 2025-12-18研 修 令和7年度名簿登録研修について
- 2025-12-18事務局 年末年始休業のお知らせ
- 2025-12-18募 集 2025年度スクールソーシャルワーク実践アドバイザー研究交流集…
- 2025-12-09募 集 群馬県社会福祉士会・入会促進企画 「キャリア・ミートアップ!…
- 2025-11-27募 集 【募集開始】2026年度「認定社会福祉士制度スーパービジョン」…
委員会報告
- 2025-12-10委員会等の報告 東毛地区協議会 館林散策 開催報告♪
- 2025-11-22委員会等の報告 2025年度 成年後見人材育成研修 終了
- 2025-11-18委員会等の報告 令和7年度 高齢福祉委員会 勉強会&交流会&懇親会 開催報告
- 2025-11-04委員会等の報告 TEAMオンラインで交流会的研修会を企画中!
- 2025-11-02委員会等の報告 レッツ・ホール・ハンズ第7回勉強会 開催報告